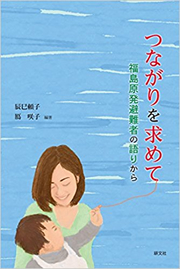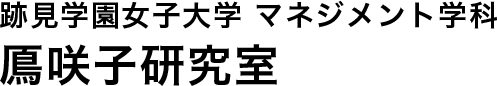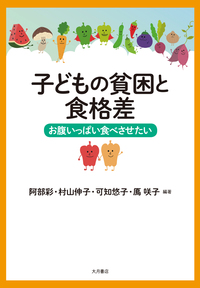| 書名等 |
発行所 |
発行年月 |
備考 |
| 「学校給食と子どもの貧困」阿部彩・村山伸子・可知悠子・鳫咲子編『子どもの貧困と食格差』
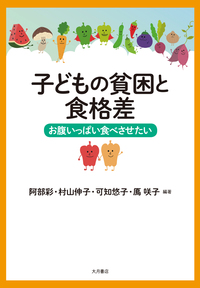
|
大月書店 |
2018/4 |
2015年の日本の子どもの貧困率は13.9%とOECD諸国の最下位クラスにある。また、ひとり親世帯の相対的貧困率は50.8%であり、2人に1人の子どもが貧困状態にある。「学校給食と子どもの貧困」をテーマに、子ども同士の格差が広がる中、貧困児童・欠食児童対象の給食から普遍的な給食に発展した学校給食の原点に立ち返って、給食費未納問題、さらには給食費無償化について論じた(p.89-p.119)。 |
つながりを求めて-福島原発避難者の語りから
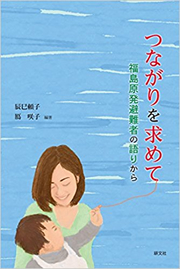 |
耕文社 |
2017/8 |
福島第一原発事故による放射線の影響を恐れ、東京に避難してきた母子避難者たち—2011年からの6年間、避難生活と先の見えない不安、家族との葛藤、そのなかでどのように〈つながり〉を求め、日常を送ってきたのか。どのような〈支援〉が求められているか。本書はその聞き取りの記録と考察である。 |
給食費未納 子どもの貧困と食生活格差
 |
光文社 |
2016/9 |
学校給食の歴史は、凶作・災害・戦争・炭鉱の閉山による大規模失業など子どもの食をおびやかす事態に日本が遭遇し、学校が子どもの貧困に対応した歴史と言える。しかし、戦後の混乱が落ち着いて高度成長期に入った1960年以降の50年間、学校は子どもの貧困を解決すべき主要な課題と考えなかったように見える。地域によっては、長年、中学校給食の実施が見送られてきた。給食費未納問題も、まずは親のモラルの問題と扱われてきた。子どもの貧困対策では、義務教育学校である小中学校という「プラットフォーム」を十分に活用し、福祉的支援につなげることが必要である。 |
「被災した子どもの教育支援」青木栄一編『復旧・復興へ向かう地域と学校』
 |
東洋経済新報社 |
2015/12 |
東日本大震災では、被災した子どもに対してNPOはじめ多くの団体・組織が支援活動を行っている。本章では、経済的支援として、奨学金・給付金など被災者個人への金銭の支給、貸付金の貸付けなど、子どもの教育のための経済的負担を軽減する現金給付を主として分析の対象としている。被災した家庭の子どもの教育のための経済的負担を軽減する経済的支援は、大規模災害の発生時においても子どもに教育の機会均等を保障する観点から重要である。 |
子どもの貧困と教育機会の不平等:就学援助・学校給食・母子家庭をめぐって
 |
明石書店 |
2013/9 |
世界的にみても深刻な日本の現状を踏まえ、2013年6月、「子どもの貧困対策法」が成立した。給食費未納問題、就学援助の現状など、主に教育費用と貧困問題について多角的に検証し、子どもの貧困削減のための政策を考える。 |
国民教育文化総合研究所 東日本大震災と学校資料収集プロジェクトチーム編『 資料集 東日本大震災・ 原発災害と学校』
 |
明石書店 |
2013/9 |
東日本大震災発生と大津波、大規模原発災害。日本の学校現場にとって未曾有の大災害が発生したなかで、学校現場は、行政はどのような対応をとったのか。被害の把握、教育現場の再生…、混乱と人的、物的な大被害のなかで残された貴重な記録を収集・編集した。 |
「就学援助制度における自治体間格差」子どもの貧困白書編集委員会編『子どもの貧困白書』
 |
明石書店 |
2009/8 |
教育の機会均等という就学援助制度の目的に対して十分な運用が各自治体で行われているかを検証するためには、まず文部科学省が市町村の運用実態に関わるデータについて、ホームページ・白書等で広く国民に情報提供することが、その第一歩である。 |
「「大規模な公共施設の立地問題について―我が国立法と英米における考え方との相違― 」大浜啓吉編『公共政策と法』
 |
早稲田大学出版部 |
2005/8 |
わが国には、ダム、発電所など大規模な公共施設の立地を円滑に 促進するため、施設の周辺地域の整備を行う法律がある。英国の 計画法制は、計画の策定において地方政府に主たる権限がある。 米国では、収用事業者の裁量権の行使に濫用がないかどうかを司 法審査に委ねるという考え方が採られている。我が国の計画法制 は、英国に倣った部分が多いが、開発権の公有化、計画の実質的 な情報公開については、現在の我が国法制には取り入れられてお らず、今後の検討課題である。 |
「地方自治体とまちづくり―志免町給水訴訟を例として―」大浜啓吉編『都市と土地政策』
 |
早稲田大学出版部 |
2002/2 |
給水規制規則を制定した事例に見るように、地方自治体に国の権 限を移譲することで現在のまちづくりの問題が全て解決するわけ ではない。地方自治体における住民参加手続に関しては、以下が 指摘できる。多くのまちづくりは、計画に基づいて行われるが、 計画によるまちづくりにおいては、事後的な司法救済が十分に機 能しない。行政機関が計画を策定する際には、広い裁量が生じ る。この裁量を統制し、計画の合理性を担保するためにも、事前 の計画決定に関する住民の参加は必要不可欠である。 |
| 「まちづくり法の立法論的考察―土地利用計画策定過程における適正手続―」矢崎幸生編『現代先端法学の展開:田島裕教授還暦記念』 |
信山社出版 |
2000/7 |
地域住民が守ろうとする利益は、まちづくりの理念として市町村 の条例として定めることにより、公益的な利益として特定され、 司法的な救済の対象となる。このことにより、市町村において現 在よりも地域住民にとって暮らしやすいまちづくりを行うことが 担保できる。 |
| 「日本の土地法制について」「土地担保金融と地価高騰」「まちづくりを実現するための法律」奈良次郎・吉牟田勲・田島裕編『土地利用の公共性』 |
信山社出版 |
1999/4 |
土地法制をめぐる今日的諸問題のうち、日本の土地法制につい て、土地担保金融と地価高騰、まちづくりを実現するための法律 についての 研究である(p.3-p.14)、(p.107-p.116)、(p.283-p.299)。 |